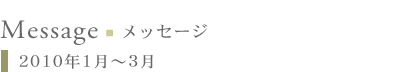
ホームページをご覧の皆様へ |
|
|
 |
||
飯守泰次郎です。東京シティ・フィルの2009−2010シーズン定期を締めくくる第237回定期演奏会(3/18)では、ハンガリーの作曲家のみによる一晩という、非常にユニークなプログラムをお届けします。
最初に演奏するのはコダーイの「管弦楽のための協奏曲」です。念のために申し上げますと、バルトークにも同じ名前の大変有名な作品がありますが、今回とりあげるのは同じハンガリーのコダーイの作品で、めったに演奏される機会のない曲です。
コダーイのオーケストラ作品というと「ハーリ・ヤーノシュ」と「ガランタ舞曲」はよく知られていますが、実は他にもたくさんのオーケストラ作品があります。 この「管弦楽のための協奏曲」は、シカゴ交響楽団の創立50周年を記念して1939年から1940年にかけて作曲されました。
単一楽章から成り、古いハンガリーの民謡を思わせる五音音階が頻繁に使われています。
ハンガリーの音楽といえば、跳躍するような勢いのあるリズムが特徴的で、この作品もリズミックでオーケストレーションも色彩に富み、非常にエネルギーに満ちた躍動的なメロディが魅力的で、民族色が大変豊かです。
そして、曲名が示すとおり各楽器がソリスト的に扱われており、小さな楽器群とオーケストラ全体のトゥッティ(全奏)との対照が鮮やかです。
もっともっと演奏されてよい素晴らしい作品だと考え、バルトークと組み合わせて今回演奏致します。
「青ひげ公の城」は、バルトーク唯一のオペラです。ヨーロッパ各地の歴史に長く伝わる、男女の愛に関する伝説をもとに、ハンガリーの詩人バラージュがテキストを書き、バルトークが作曲しました。
あえて極端な言い方をするならば、ヨーロッパの音楽の源泉は、宗教音楽の歴史と、通俗音楽の歴史という2つの流れから来ています。
このうち通俗音楽の歴史というものは、言い換えれば男女の愛というものが非常に大きな内容を占めています。
「青ひげ公の城」は、この男女の愛の問題を非常に深く掘り下げた作品です。
19世紀の芸術は、世紀末を迎えてついに崩壊へと向かいますが、そのなかでもこれは、男女の愛というテーマを扱った最も極端な作品のひとつであり、いわばひとつの頂点、あるいは極をなしていると思います。
おそらく、この作品を聴いて幸せになる人はいないでしょう。 男女の愛というテーマを1時間に凝縮し聴き手を震撼させるこの作品は、バルトークがまだ非常に若いころの作品です。しかし、すでに彼のその後の全生涯がここに凝縮されているのです。
バルトークの感性の異常なまでの鋭さ、ハンガリー語の響きと結びついたオーケストラの民族的な響き…彼の才能には驚嘆するほかありません。
バルトークの生涯は決して幸せではなく、病気と貧困に悩み、アメリカに渡って悲劇的な死を遂げました。まだ若いときの完璧ともいえるこのオペラは、むしろ彼の不幸な一生の前兆のようにさえ感じられます。私は、この作品を演奏するたびにますます、その魅力の虜になるのです。
私と東京シティ・フィルは、ドイツ・ロマン派の作品から近現代までの数々の作品を演奏してきて、このような特殊な作品を演奏する能力もおそらくしっかり身につけてきていると感じます。
皆様に恐ろしい「青ひげ」をお届けできるのではないかと思います。オペラシティでお会いしましょう。
関西フィル第217回定期(2/19)に向けて |
|
|
 |
||
 |
飯守泰次郎です。今年、関西フィルは、記念すべき創立40周年を迎えます。
その幕開けとなる2月の定期演奏会では、マーラー生誕150年に際して交響曲第2番『復活』という大曲に挑みます。
合唱団は、声楽作品で関西フィルと数多く共演している大阪アカデミー合唱団と、関西二期会合唱団の合同で、総勢約200人という大所帯です。
この交響曲における合唱団の重要性は、申し上げるまでもありません。 本番まで約半月となり、全力投球で取り組んでいるところです。
 |
2/19にはぜひ、ザ・シンフォニーホールでお目にかかりましょう!
関西フィル いずみホールシリーズVol.18 (2/6) |
|
|
 |
||
 |
飯守泰次郎です。昨春から全4回のシリーズでお送りしている、関西フィルとのいずみホール“The Discovery・飯守泰次郎と巡る奇跡の音楽史”シリーズも、最終回となりました。
第1回ではイェルク・デームスさんをお迎えして“ベートーヴェンの継承”(2009/4/9)、第2回は“生誕200年 メンデルスゾーンの古典美”でオーギュスタン・デュメイさんと共演(9/17)、そして第3回は関西出身の作曲家・大澤壽人ゆかりの“1930’s
輝けるフランス”で迫昭嘉さん(11/3)、と毎回大変素晴らしいソリストの方々とご一緒してまいりました。
非常に色彩豊かなこのシリーズの最終回となる今回は、“ロシアの雄渾”と題してチャイコフスキー・プログラムをお届けします。
歌劇「エフゲニ・オネーギン」から“ポロネーズ”、ヴァイオリン協奏曲ニ長調、そして交響曲第5番、という、チャイコフスキーの中でも最もポピュラーな作品ばかりを集めたプログラムで、どなたにもお楽しみいただけると思います。
今回のようにあまりに演奏機会の多い名曲は、ややもすると演奏する側もお客様も新鮮さを感じられなくなっていることがあります。今回私は思い切って、自分がこれまで演奏したことがないようなチャイコフスキーに、新たな気持ちで取り組んでおります。
関西フィルの楽員たちもそのことをよく分かってくれて、応えてくれることを非常に嬉しく思います。とてもよい音楽会になる予感がしています。
ソリストの大谷玲子さんは、今までも何度も関西フィルと非常に気の合った演奏をしてくださっています。もはやベテランの域に達していると申し上げるべきかもしれませんが、今回も彼女のさらなる成長ぶりを大変楽しみにしております。皆様をいずみホールでお待ちしております。
ホームページをご覧の皆様へ |
|
|
 |
||
 |
飯守泰次郎です。先日ご紹介した日本フィルの定期を、おかげさまで無事終えることができました。
一夜めの集中度も良かったですし、二日目も表現力が増してより発展した演奏ができ、いずれも大変ご好評いただきました。
以前から、日本フィルとは何年に一度か必ず定期演奏会でご一緒しています。今回感じたのは、表現力に非常に幅が出てきたということです。
今回のように特にコントラストのはっきりしたプログラムでは、それぞれの曲目に合った表現が必要になります。
響きの面でも、ブラームスのサウンドと湯浅作品のサウンドは全く異なりますし、さらに小山作品では独創的な古い日本のサウンドが求められます。
これらのコントラストを、オーケストラが見事に表現してくれたことを、大変嬉しく思っています。聴衆の反応が大変温かいことにも、深い印象を受けました。
日本フィルは恐ろしいほどのスケジュールを精力的にこなしているオーケストラですが、雰囲気がとても和やかでいられることも素晴らしく、そのことにも、客演するたびに感銘を受けるのです。
ホームページをご覧の皆様へ |
|
|
 |
||
 「奥の細道」リハーサルにて〜湯浅譲二先生と |
飯守泰次郎です。本日と明日は日本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会を指揮します。
今回は、日本人作品2曲、そしてブラームスの交響曲第4番という、全くキャラクターの異なる非常にユニークな組み合わせであり、ぜひご案内をしたいと思います。
小山清茂さんの「管弦楽のための鄙歌第2番」は、日本人作品の中でもきわめて素朴であり、日本という国と民族の持つありのままのごく自然な音楽性を表現しています。
豊作を祝うお祭りや、菩薩が天から降りてきて地上でなごむ、というような内容が、ごく普通のオーケストラに四つ竹、絞太鼓、桶胴、やぐら太鼓などを加えて賑やかに展開され、文句なしに楽しめる愛すべき作品です。
今回この「管弦楽のための鄙歌第2番」は、“日本フィル・シリーズ再演企画”の第4弾としての選曲です。
これまで日本フィルは、「日本フィル・シリーズ」と題する新作委嘱のシリーズで、この「管弦楽のための鄙歌第2番」をはじめ50年間に40作もの優れた新作を生み出してきました。 日本の管弦楽作品のレパートリーを真に身近で豊かなものにしていくには、新作として生まれた作品を繰り返し再演して育てていくことが極めて重要なのですが、実際にはその機会は非常に少ないのが現実です。それだけに、再演に焦点を当てたこの日本フィルのシリーズは、大変に価値のあることなのです。
湯浅譲二さんの交響組曲『奥の細道』は、以前に演奏してCDも録音している、湯浅さんの作品の中でも特に大好きな曲です。
特別な魅力を持つ芭蕉の俳句のなかから4つを選んで題材とした組曲で、作曲家がいかに芭蕉の偉大さに魅せられているか、ありありと伝わってきます。
俳句というのは本来は季節感をもつ短い詩であるわけですが、芭蕉の俳句は、季節感を超えた大自然の偉大さ、時空間を超えた拡がりを感じさせる、哲学的な内容を内包しているところが特別な魅力です。
 湯浅譲二先生と |
湯浅さんの作品は、オーケストラの編成も大きく、現代オーケストラの機能性と音色の表現の可能性を最大限まで使っていながら、一方でいにしえの日本を感じさせるところが素晴らしいと思います。
この曲を練習していると、この曲はものすごく昔からあったのではないか、と感じる瞬間があるのです。あるいは、1つの音がスーッと鳴るとき、1つの和音が響くときに、この1つの音に世界のすべてが入っている、と感じることがあります。
このように感じるのも、湯浅さんの作品が芭蕉の本質に真に肉迫しているからこそと思います。
湯浅さんは80歳を超えておられますが非常に若々しい感覚で、円熟の中でなお最先端を行っておられるところは私には驚異的です。
今回もリハーサルに立ち会ってくださっていて、疑問を感じたところはすべて分かりやすく説明してくださるので、そのことも私にとって大変な喜びです。
さて、ブラームスの交響曲第4番は、いうまでもなく彼の最後の交響曲です。
ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンが若いころから交響曲を作曲していたのと比べ、ブラームスは、40代という円熟を迎えて初めて交響曲第1番を完成しました。
彼が、ベートーヴェンの9つの交響曲を聖書に例えたことは有名です。ブラームスは、ベートーヴェンを継承してドイツの交響曲の伝統をさらに進めることが自分の務めであると考えていたのです。自分に課したそのあまりの重圧のために、第1番を発表するまでに約20年かかったのです。
そして、ブラームスの欲した内容が交響曲第1番、第2番、第3番…となって、彼の音楽と人間性が最終的に到達したのが、この第4番の交響曲であり、これがこの作品を演奏するうえで最も難しいところです。
交響曲第4番は、ドイツの交響的な音楽のひとつの到達点という高みにあり、同時に彼自身の人間として作曲家としてのすべてが集約されているのです。
後期ロマン派の交響曲作家としてベートーヴェンが交響曲において成し遂げたことをさらに推し進めると同時に、過去のドイツ音楽のすべてを振り返り包括していることも、ブラームスの偉大さです。
この交響曲第4番に向き合うことは、私自身としても避けて通れない道であり、大変荷が重いことなのです。
ブラームスの生涯を私なりにたどっていくと、その偉大な存在に畏敬の念を新たにするとともに、彼の人間的な側面に非常な親密さを覚えます。極端にいうと育ての父親、あるいはいつもそばにいてくれるおじさん、のような温かさを感じるのです。
最近の日フィルは、まさにブラームスの音といえる響きが出るようになり、これも私にとっては大変嬉しいことです。
本日と明日のユニークなプログラムを、ぜひお楽しみいただければと存じます。サントリーホールでお待ちしています!
ホームページをご覧の皆様へ |
|
|
 |
||
 クロチャンも一緒に寅年を迎えました |
ホームページをご覧くださっている皆様、明けましておめでとうございます。
クロチャンも一緒に、新年を迎えました。クロチャンはトラねこではありませんが、せめて私が縞のシャツを着て寅年を祝っております。
こんな調子ですが、今年もクロチャンが元気に素晴らしい1年を過ごせるよう、みなさまも見守っていただければ幸いです。
 |
新年最初の本番は、名古屋二期会のニューイヤーコンサート(1/10)です。オペラの中の名曲・名場面が盛りだくさんのコンサートで、すでに11月からピアノ稽古を重ねています。イタリア、フランス、ドイツのさまざまなオペラから、アリア、重唱、名場面をお送りします。
ぜひホールでお会いしましょう。

(c) Taijiro Iimori All Rights Reserved.